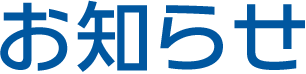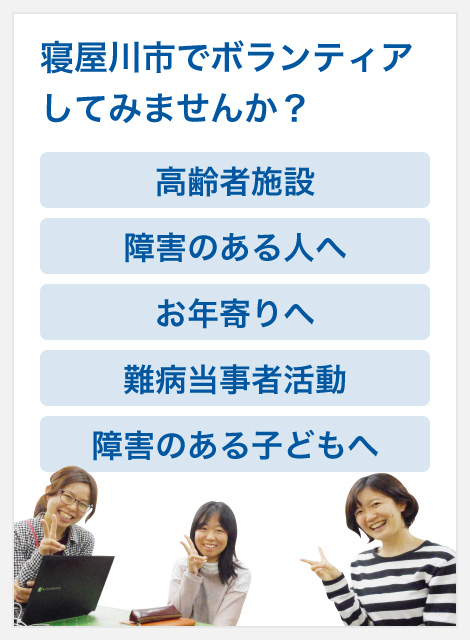お電話での受付 平⽇10:00〜17:00
地域の公共冷蔵庫-寝屋川コミュニティフリッジ
プロジェクト情報
食品ロスをなくすために 新たな「たすけあいのネットワーク」をつくるために寝屋川市民たすけあいの会は寝屋川コミュニティフリッジ・プロジェクトに取り組んでいます
寝屋川コミュニティフリッジのページ
数年前から「コミュニティ・フリッジ」(フリッジは「冷蔵庫」のこと)とよばれる取り組みが欧米各地にひろがっているそうです。フードロス、いわゆる食べずに捨てられる食品や材料をなくす運動は2030年をめざした国際的な取り組み「持続可能な開発目標 SDGs」にも合致した取り組みです。
何もしなければ廃棄されてしまう商品を消費者のニーズとマッチングさせることで食品ロスの発生や、無駄を減らす仕組みです。
欧米では文字通り公共の場に設置された大きな冷蔵庫に個人や飲食店が不要な食べ物を冷蔵庫に入れて、その食べ物は誰でも持って帰ることができるという取り組みや公共施設を借り、定期的にスーパーなどからの食品を配布する(日本でいえば、フードパントリーのような)な取り組みだそうです。街角に冷蔵庫をポンと置くということは、衛生観念や食品の取り扱いの文化の違う日本ではなかなか同じようにはいきません。
それでも日本に合う仕組みとして、2020年の秋に岡山で「北長瀬コミュニティフリッジ」が立ち上がりました。
地域の住民とお店が一緒になってフードロスを減らす取り組み。昨今の社会事情から、フードバンク(一方に余っている食べ物があり他方で食べ物に困っている人がいてそれをつなぐ活動)の一つの形としても世界で拡がっているそうです。
私たちはコロナ禍が続き、地域での問題がどんどんと見えなくなってきているように感じてます。【ほんとうに困っている人が声をあげることができにくい】そんな社会になっているように感じます。
いつのまにか、「支援する側」と「支援される側」を分断するような社会になってしまっていて、「支援をうけるハードル」がどんどん上がっているように思います。そんな現状に取り組むために日本型「コミュニティフリッジ」を寝屋川に作るプロジェクトを立ち上げ、2021年に「寝屋川コミュニティフリッジ」を開設しました。
【食品ロス解消】と【ひとり親家庭とそのこどもさん/生活困窮者支援】のバランスをとっていくことに取り組みながら、活動を拡げてきています。
2023年9月から、農林水産省のフードバンクリストへの掲載をはじめ「フードバンク」としての機能をもつようになりました。市内の「子ども食堂」さんや「こどもさん支援」を行っている団体さんと連携し、食品の提供を行っています。
また、食品ロスに関する啓発事業として、2023年8月と12月には、「子育て応援フードパントリー」を。アルファ化米活用プロジェクトも行っています
関連記事
- 2026.02.10お知らせ つなぐ284号発行しました
- 2026.02.01お知らせ 今月(2026年2月)のフードドライブの予定です
- 2026.01.23お知らせ スーパーバロー 寝屋川2店舗でフードドライブがはじまります
お問い合わせ
MENU
最新情報一覧
-
2026.02.10お知らせ
つなぐ284号発行しました -
2026.02.01お知らせ
今月(2026年2月)のフードドライブの予定です -
2026.01.23お知らせ
スーパーバロー 寝屋川2店舗でフードドライブがはじまります

 072-826-4655
072-826-4655